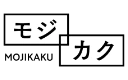クラスメソッド社の事例記事に学ぶ。年間50本以上の公開を支える体制とパートナーに求める資質とは
- 事業規模:500名〜999名
- 業種:情報・通信業
- 課題:事例記事を量産できていない

クラウドサービスやデータ分析、生成AIといった幅広い技術領域で企業のDXを支援するクラスメソッド株式会社。同社では営業・マーケティング施策の中核のひとつに「事例」を据え、年間50本以上という高い頻度で事例記事を制作、発信しています。その背景には、自社内の制作体制に加えて外部の協力パートナーとの連携があります。
今回は、同社の営業統括本部 デジタルマーケティング室でコンテンツディレクターを務める鵜飼 亮次氏に、継続的に事例記事を制作する背景やこだわり、制作体制を支える協力パートナーに求める資質、そしてモジカク株式会社との取り組みについて、お話を伺いました。
<お話を伺った方>
クラスメソッド株式会社
営業統括本部 デジタルマーケティング室 コンテンツディレクター
鵜飼 亮次氏
目次
“週1本”が目安の高頻度な事例発信。幅広い技術領域の事例が、顧客価値を可視化する
クラスメソッド株式会社(以下、クラスメソッド社)では、自社サービスを導入した顧客企業の導入事例を積極的に発信しています。同社の公式Webサイトの「事例」ページでは、これまでクラスメソッド社が支援した顧客の導入・活用事例がインタビュー形式で紹介されており、取り組みごとの具体的な課題や提供したソリューション、そして導入後の成果がまとめられています。
こうした事例記事の制作に取り組んでいるのが、同社のデジタルマーケティング室です。高頻度かつ高品質な事例記事の公開を支える立役者のひとりであり、実際に自身の業務の大半を事例制作に費やしていると語るのが、コンテンツディレクターを務める鵜飼 亮次氏です。
「弊社では事例記事の制作におけるKPIとして、『1週間に1記事の事例公開』を掲げています。短期的な目標として、イベントや展示会への出展から逆算して新しいサービスの事例記事を集中的に作成することもありますが、基本的には継続的に事例記事を積み上げていく方針です」(鵜飼氏)

こうした高い制作頻度の背景には、クラスメソッド社がカバーする技術領域の幅広さがあります。AWSに代表されるクラウドプラットフォームから、個別のSaaSまで多岐にわたるソリューションを提供していること、さらに最近では生成AIの活用支援という新たなサービス展開も、事例記事の量産の追い風になっています。
事例記事は企業の資産。業界特性と定性・定量の成果の描写が、読者に説得力をもたらす
クラスメソッド社では、事例コンテンツをBtoBマーケティング施策における基点のひとつと位置づけ、営業資料やセミナー配布物、ホワイトペーパー、Webサイト掲載など多様なチャネルで活用し、長期的な資産として蓄積しています。特に2023年に実施されたWebサイトリニューアルではトップページのファーストビュー、つまり最初に目に入る部分に大きく事例記事への導線を配置しました。これはクラスメソッド社が事例記事を重視する姿勢を象徴するものだと、鵜飼氏は話します。
「技術を通じてお客様への貢献を目指す当社にとって、導入事例を通じて支援の価値を伝えることが、サービスの比較検討をされている見込み客に対する強力な後押しとなります。単なるストーリーとして事実を並べるのではなく、顧客の感情や変化をナラティブとして記事内で描くことが事例記事としての説得力を生み、BtoBマーケティングの成功を後押しする原動力になると考えています」(鵜飼氏)
業界ごとのアプローチもクラスメソッド社における事例活用の特徴的な側面です。各業界ごとに知名度が高い企業を優先して取材し、業界ならではのポイントを抑えた記事を執筆することで読者の自分ごと化を狙っています。

クラスメソッド社の事例制作において重視されているのが、定量的な成果と定性的な成果の両方を適切に表現することです。特にコスト削減や処理時間の短縮といった数値的な成果は、比較検討段階の見込み客にとって最も魅力的な情報となります。ただ、数値だけでは表現しきれない価値の言語化も、同様に重要だと鵜飼氏は指摘します。
「クラウドサービスの導入支援という性質上、単なるサービスの事例としてではなく、クラスメソッドならではの提供価値を明確に示す必要があります。たとえば、担当したエンジニアの専門性やプロジェクト進行におけるサポートへの評価など、人の手による支援ならではの価値を具体的なエピソードとして描写することが求められます」(鵜飼氏)
協力パートナー選定が、高頻度かつ高品質な事例制作を支える
高頻度かつ高品質の事例制作を実現するため、クラスメソッド社は内製と外部委託を戦略的に使い分けていることが特徴です。業務委託で契約しているライターやカメラマンとのネットワークを構築し、案件ごとにチームを編成して対応しています。地方企業への取材ではその地方で活動するカメラマンをアサインしたり、撮影・取材をまるごと委託したりと、スピード感ある事例制作を実現するため、外部の協力パートナーを巻き込んでいるとのことです。事例制作の協力パートナーを選定する上での基準について、鵜飼氏は専門性、納期管理、コミュニケーションの3点を挙げます。
① 専門性
「ITインフラを構成する階層ごとに直面する問題点や解決すべきテーマ、それに対する解決策を体系的に把握し、お客様の発言に対して適切に反応できる能力が求められます。これは単なる技術用語では不十分で、IT技術を伴う実務相当の細かな理解が重要です。特にクラウド技術やデータ分析といった専門性の高い分野では、この要件がより厳しくなると考えています」(鵜飼氏)
② 納期管理
「SEO記事といったコンテンツの制作とは異なり、事例記事の制作では私たちのお客様のスケジュールが最優先です。そのため、柔軟なスケジュール調整能力と、確実な納期の遵守が求められます。量産制作を支えるには、ご依頼から公開までのやり取りが最小限で済む効率的なワークフローと安定した品質の両立が不可欠です」(鵜飼氏)
③ コミュニケーション
「お客様は私たちにとって最も大事な存在です。そのため、名刺交換から始まる基本的なビジネスマナーはもちろん、取材進行における適切なコミュニケーション能力が求められます。この社会人基礎力が充分であると確信できて初めて、安心して取材をお任せできるのです」(鵜飼氏)

単なる執筆代行にとどまらない。編集的視点をもった外部パートナーが事例の質を高める
クラスメソッド社では、導入事例制作の一部を外部の協力パートナーであるモジカク株式会社に委託しています。取材・執筆にとどまらず、案件ごとに編集会議を実施し、「読者はどのような情報を求めているか」「どのようなエピソードと成果を深掘りすべきか」といった企画の工程に加え、カメラマンのアサインから修正作業までお取り組みしてきました。モジカク株式会社との取り組みに対して、どのように評価いただいているのかお聞きしました。
「特にありがたいのは、我々の要望を的確に汲み取って記事に落とし込んでくださる点です。単なる書き起こしや執筆ではなく、『特にこの点は強調すべきだ』といった編集的な観点を加えてくださるので、安心してお任せできます。
私たちの状況に合わせて、柔軟に対応していただける点も助かっています。モジカクさんに依頼すると、ご依頼時に希望した記事テーマに沿った内容で納期通りに原稿を仕上げていただけます。社内やお客様からの修正・変更依頼についても丁寧にキャッチアップしていただけるので、まさに伴走型のパートナーといった印象です」(鵜飼氏)
生成AI時代における理想の協力パートナー像。クラスメソッド社が重視する資質と役割とは
クラスメソッド社では現在、全社規模で生成AIを積極的に導入しており、事例制作においても文字起こし作業の効率化や文章校正など活用を進めています。事例記事の制作体制は、今後さらに効率化され、生産性が高まっていくと話す鵜飼氏に、今後の展望を伺いました。
「将来的には、すべてのユースケースを事例化していきたいですね。新たに始まった生成AIの支援サービスをはじめ、事例の題材は尽きませんので、数と質の両面を高めながら事例を増やしていく予定です。
また、事例記事は営業やBtoBマーケティングだけでなく、企業ブランディングにも直結するコンテンツです。事例に登場いただくお客様の声を通じて、サービス品質や支援するメンバーのスタンスなども感じていただきながら他社と差別化していきたいと考えています」(鵜飼氏)

生成AIの活用で事例記事の量産体制を整える一方で、取材対象者の微細なニュアンスを捉える必要がある取材そのものや、記事執筆の核心部分については、生成AIによる完全な代替は困難であると鵜飼氏は指摘します。顧客との直接的な対話を通じて引き出される微細なニュアンスや、言語化が困難なサービス提供価値の発見は、依然として人に依存する領域です。取材の最後に、生成AI時代における事例制作パートナーはどのような姿勢を持つべきか、お聞きしました。
「今後の協力パートナーに求めるのは、単に『手を動かしてもらう』のではなく、より付加価値の高い作業、つまり価値の言語化やより最適な記事構成の企画など一緒に取り組んでいただく姿勢です。
そのうえで、モジカクさんの協力パートナーとしての誠心誠意な対応を評価しています。よりよい事例制作のためにトラブルは避けられませんが、それをどのように解決するかが重要であり、そこにこそ協力パートナーとしての真価が表れるのではないでしょうか」(鵜飼氏)
モジカク株式会社の導入事例制作サービスは、年間200件以上の豊富な実績をもとに、企画から取材、撮影、執筆までを一気通貫で対応します。営業やBtoBマーケティングなど幅広い場面で活用できるだけでなく、企業の資産となる事例記事を制作します。
導入事例の制作に悩んだら、ぜひモジカク株式会社にご相談ください。
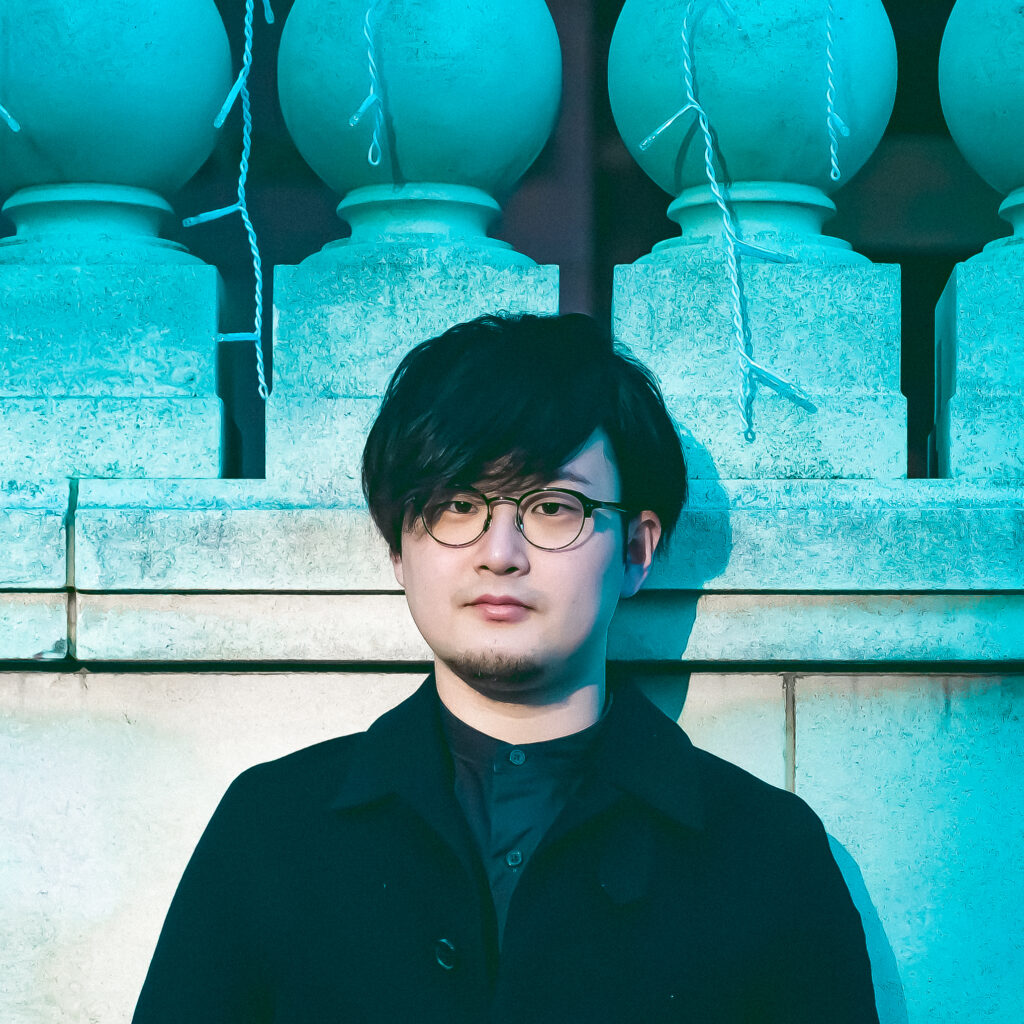
大木一真/Kazuma Oki
株式会社サイバーエージェントに新卒入社。ビジネスメディア「新R25」立ち上げチームの編集者として参画。退職後、株式会社AViC(東証グロース)創業期より執行役員を務める。その後独立し、編集プロダクションであるモジカク株式会社を設立。Forbes JAPAN や MarkeZine 等のビジネスメディアやSaaS企業の導入事例を中心に執筆活動を行なう。
Twitter:@ooki_kazuma
facebook:kazuma.ooki